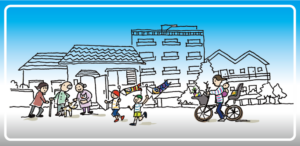
あらまし
- さまざまな事情から住まいの確保に特に配慮を要する「住宅確保要配慮者」。社会変化に伴い、その属性や状況、ニーズ等は多様化しています。この間、住まい支援に関する法改正がすすみ、「住宅」と「福祉」分野が連携して取り組むことが求められています。本連載では、居住支援の現場を取材し、課題や必要な取組みを明らかにしていきます。第1回目の今号では、教授の白川泰之さんに「居住支援のこれからと今後」について寄稿いただきました。
住宅と福祉の新たな局面
住宅確保に課題を抱える人々への対応について、社会福祉政策と住宅政策との関係は、2022年の12月に大きな転機を迎えました。「全世代型社会保障構築会議」の報告書の中で、地域共生社会の実現のために取り組むべき課題として、「住まい政策を社会保障の重要な課題として位置づけ」ることが明記されたのです。さらに、厚生労働省、国土交通省、法務省の三省合同で設置された「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会」が2024年2月に中間とりまとめを行い、「福祉施策と住宅施策が緊密に連携し、相談から住まいの確保、入居後の支援までの一貫した総合的・包括的な支援体制」の構築を基本的方向性として掲げ、具体的な取組みを列挙しました。
その後、生活困窮者自立支援法等や、いわゆる住宅セーフティネット法が改正され、居住支援の充実が図られることになりました。日々の相談支援業務で支援対象者の「住まい」の問題解決に迫られ、苦労された経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。これからは、住まいの問題は住宅政策と社会福祉政策の共通の政策課題として受け止め、その解決に向けた連携が大幅に強化されることになります。住まいを確保し、さらに入居後の暮らしを一体的に支える居住支援が新たなステージに入ったのです。まさに、新時代の幕開けです。
関係改正法の概要
社会福祉の分野では、まず、生活困窮者自立支援法において、自立相談支援事業で新たに「居住」に関する相談支援が位置付けられました。また、一時生活支援事業は「居住支援事業」に改称されるとともに、そのうち必要があると認めるものを行うことが努力義務となりました。また、社会福祉法では、重層的支援体制整備事業について、居住支援協議会等と緊密に連携しつつ、居住の安定の確保のために必要な支援を行うよう努めることになりました。
一方、住宅政策の分野では、住宅セーフティネット法が改正されました。この法律は、高齢者、障がい者、低所得者など住宅の確保に特に配慮を要する「住宅確保要配慮者」(以下「要配慮者」)の賃貸住宅への入居の促進のための法律です。同法は、これまで国土交通省の所管でしたが、法改正で多くの事項が厚生労働省との共管となり、社会福祉との結びつきが強められました。また、地域での居住支援の体制整備の核となる居住支援協議会の設置が、任意から地方公共団体の努力義務とされ、かつ、要配慮者の福祉サービスの利用に関する相談体制の整備、生活の安定及び向上の施策との連携が協議事項として追記されました。
さらに、この協議会の構成員として、社会福祉協議会など要配慮者の福祉に関する活動を行う者も条文上追記されました。特に要配慮者の暮らしを支える面で、読者の方々が相談支援の第一線で把握してきた課題やきめ細かに展開されてきた各種の事業を地域の居住支援体制の整備に還元していくことが、より一層期待されることになります。
「生きる力」を引き出す居住支援を
これまで厚生労働省や国土交通省のプロジェクトで、市町村の居住支援協議会設立のお手伝いをしてきました。その中で見えてきたのは、住まいと暮らしの安定が、ただ雨風をしのげる安心感にとどまらず、その人の生きる力を引き出すということです。もちろんケースにもよりますが、社会生活自立や就労自立につながることも珍しくはありません。また、入居前後を通じて支援に当たった社会福祉法人の施設でボランティアをするようになった高齢者など、支える・支えられるという関係も固定的ではありません。今後、地域共生社会を実現していく上で、人々の暮らしを再構築する「居住支援」は、重要なキーワードとなっていくでしょう。

足立区居住支援協議会や「居住支援協議会伴走支援プロジェクト」の委員等をされている。








