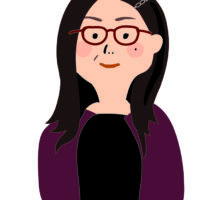(社福)立川市社会福祉協議会 地域活動推進課 地域づくり係
ボランティア・市民活動センターたちかわ
(左から)センター長 小山 泰明さん、主任 小林 伸匡さん
あらまし
- 子ども・若者がこれからを生きていく上で“福祉”が身近な存在であってほしい。
本連載では、そうした思いで次世代に向けて取り組む団体や地域を取り上げます。第1回は立川市社会福祉協議会「ボランティア・市民活動センターたちかわ」による大学生を対象とした「Social Sketch Lab.」についてお届けします。
(社福)立川市社会福祉協議会ボランティア・市民活動センターたちかわでは、大学生と社協が一緒になって地域課題に目を向け活動する「Social Sketch Lab.」(以下、ラボ)という取組みを行っています。2年目になる2025年は3人のメンバーが参加し、1~2か月に1回のペースで活動しています。
学生の持つボランティア観がきっかけに
ラボは、学生からボランティアをすることに対して「得意なことがない自分には務まらないのでは」、「『ボランティア』という言葉にハードルを感じる」などのイメージがあるという話を聞き、ボランティア観に対して、学生と一緒に研究や試行錯誤をしていきたい、という思いから生まれた取組みです。
「今までもいろいろなボランティアの企画を行ってきましたが、なかなか大学生と継続的な関わりには発展しづらく、大学生を巻き込む新しいきっかけが必要だと感じていました」。そう話すのはラボの立ち上げから携わっている小林伸匡さんです。
大学ボランティアセンターのコーディネーターとも情報交換を行う中で、既存のボランティア以外に自分たちで何か活動を立ち上げたいと考えている学生もいることがわかり、構想の後押しになりました。立川市には大学は多くはありませんが、立川市自体は交通の便が悪くないので、フィールドさえあれば「やりたい」と思う人はいるのでは、と考えこの取組みに結びついたそうです。活動を通して学生自身が自分軸での生き方を描いていくきっかけになればという思いもあり、「Social Sketch Lab.」と名づけました。この名前には「実験的に試行錯誤しながらやっていきたい」という思いが込められています。
「自分軸での生き方を探っていく」
ラボの参加条件は「立川で何かしてみたい大学1~4年生」のみ。社会福祉学を学んでいるかどうかは問いません。そのため、大学、学年、専攻している分野も異なる学生が集まります。「学んでいる分野によってそれぞれの課題意識や地域を見る視点など、濃淡は確かにあります。でもそれは意識の向け方の角度が違うだけ、と捉えています。少子高齢化や貧困問題など、福祉で取り上げられやすい課題ではなく、例えば街おこしや企業とのコラボレーションなどの目線の向け方は福祉以外の学問を専攻している学生から出てきたりしています。その足並みを揃えていく上で、いろいろなものを出し合って『見えているものが違うね』と共有することが、そのための一歩だと思っています」と小林さんは話します。
実際に今年のメンバーも大学、学年、専攻分野や住んでいる地域はさまざまです。それでも活動が始まると、地域に向けてやってみたいことや、それに対する意見や思いが出てきて、話し合いがどんどん展開されていきます。「考えが違うようで似ているところもあり楽しい」「話がまとまって形になっていくのが楽しい」と参加したメンバーも、境遇の違う3人が同じ時間を共有し活動することに新鮮さと面白さとを感じているようです。
「今年で2年目ですが、これだ!と思う手ごたえはまだ見つかっていないように感じます。年度によりメンバーが違い、すすみ方も違います。1年活動してその成果をすぐに見出せる学生もいれば、あの時の経験が今のこれにつながったと5年後10年後にわかる学生もいますが、この1年を大人が一緒に歩んでいくことに価値があると思っています」と小林さん。「単年度で何か結果を出すことよりも、長期的に見て人生の軸になるような1つの活動になってほしい」と、同じくラボの立ち上げメンバーである小山泰明さんは話します。

安心して失敗できる社会に
SNSで成功のロールモデルが簡単に手に入るようになった一方、「上には上がいる」ということを当たり前のように見せられ、根拠なく「自分はできる」と何かに挑戦しづらくなり、失敗を経験することが難しい現代。そんな今を生きる若者や次世代の人たちに向けて小山さんはあえて「失敗しようよ」と笑顔で語ります。同時に「失敗した時に責任を引き受ける大人がいる社会が福祉的な社会」とも。
小林さんも失敗しづらい世の中になったと肌で感じているそうで、ラボの活動でも、「1年で何ができたかではなく、1年の活動を通して後々自分の意見を表明できたり、自分はこうしたいという思いを形づくっていけることが重要」と言い、それを考えるきっかけをつくることや、堂々と自分の生き方をしていいんだよと暗に伝えることがラボに関わる大人としての役割だと見出しています。
ラボのこれからについて小林さんは「何かやってみたいと思っている学生に、立川市に来ればやりたいことができるかもしれない、という印象を持ってもらえれば嬉しいです。そして活動の中で地域との関わりができた時に、その学生を見て『あんな風になりたい』とあこがれを持つ小・中学生が出てくるといいなと思います。小・中学生にとってのロールモデルになってくれたら」と話します。自分より優れた人は山ほどいると感じてしまう中でも自分のやりたいことはどこかにあるはず。それを一緒に探しながらやっていくことが大切だという思いでラボの活動を続けていきます。

活動に参加したメンバー。背後のホワイトボードには、
話し合いで出た意見が書かれています。
https://www.tachikawa-shakyo.or.jp/business-guide/skct/