両計画の期間は一致していないですが、策定においては、地域福祉計画には社協の総務課長が入り、社協のまごころプランには市の福祉総務課が入るなど、相互に委員を出し合い、常に方向性を共有することで、連携・協働した計画となっています。地域福祉計画は“行政が市民のためにどういう取り組みをするか”という行政計画である一方、まごころプランは“わたしたち”が主役の住民の活動計画であるという両計画の位置づけをともに理解し、「地域福祉計画に書かれていることを、住民の活動にどのようにつなげていこうか」、「市としてはこういう動きを望んでいるが、住民のみなさんはどうか」などといった、“誰のための計画か”を意識した補完しあった連携が進められています。その背景には、かねてより、市と社協における人的な交流が盛んであるところも大きいといいます。コンパクトな国立市という特徴があるように、“お互いに距離が近く、顔の見える関係ができている”ことも国立市の強みのひとつになっています。
(2)コロナ禍を通じて広がった地域支援~食支援・スマホ操作教室からその先へ~
国立市社協では、コロナ禍以前より食料等支援事業「くにたちフードポート」を実施しています。そのなかで、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、離職や休職によって経済的な困窮に陥った方の相談が多く入るようになりました。特に、ひとり親世帯が日々の生活に困窮し食費を削ったり、子どもたちの孤食などの食に関する問題が明らかになってきました。
そこで、社協内でできることについて考えていたなかで、地域づくりの部分でつながり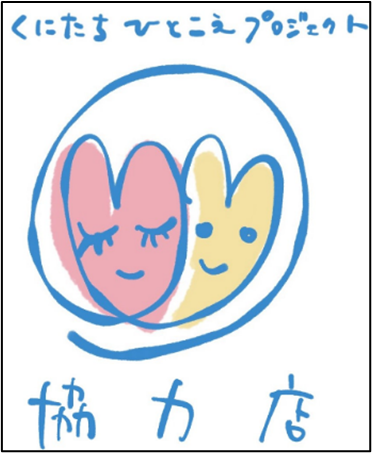 をもつ商店会の会長のところへ伺い、地域の課題について話をしたところ、“お店も苦しい状況、でも、何か子どもたちに向けた食支援はできないか”というやり取りから、市や市内飲食店の協力を得ながら、令和2年8月に、ひとり親世帯への支援「ひとこえプロジェクト(新型コロナウイルス対策緊急支援事業)」を実施しました。市内のひとり親世帯の保護者、児童を対象に1人5,000円相当の「ごはんチケット」を申込世帯に配布し、十分な食事が作れない世帯や、コロナ禍で遊ぶことができない子どもたちに、おなか一杯食べてもらいたいということを目的としたこのプロジェクトは、普段福祉に触れることが少ない飲食店も含め、市内約90店舗のうち、70近い店舗の協力が得られました。協力店舗にはステッカーを掲示し、さらに、ただの食支援だけで終わりにせず、家族でも、子ども一人でも必ず食事に来た際に「最近どうですか?」「何か困っていませんか?」と“ひとこえ”声をかける協力をお願いしました。これは、商店会からの提案でもあり、これまで一緒に関わることのなかった商店と、福祉という視点で同じ目標に向かって取り組みながら、地域で起きている課題をお互いに認識できたことが、社協としても大きな財産になったようです。
をもつ商店会の会長のところへ伺い、地域の課題について話をしたところ、“お店も苦しい状況、でも、何か子どもたちに向けた食支援はできないか”というやり取りから、市や市内飲食店の協力を得ながら、令和2年8月に、ひとり親世帯への支援「ひとこえプロジェクト(新型コロナウイルス対策緊急支援事業)」を実施しました。市内のひとり親世帯の保護者、児童を対象に1人5,000円相当の「ごはんチケット」を申込世帯に配布し、十分な食事が作れない世帯や、コロナ禍で遊ぶことができない子どもたちに、おなか一杯食べてもらいたいということを目的としたこのプロジェクトは、普段福祉に触れることが少ない飲食店も含め、市内約90店舗のうち、70近い店舗の協力が得られました。協力店舗にはステッカーを掲示し、さらに、ただの食支援だけで終わりにせず、家族でも、子ども一人でも必ず食事に来た際に「最近どうですか?」「何か困っていませんか?」と“ひとこえ”声をかける協力をお願いしました。これは、商店会からの提案でもあり、これまで一緒に関わることのなかった商店と、福祉という視点で同じ目標に向かって取り組みながら、地域で起きている課題をお互いに認識できたことが、社協としても大きな財産になったようです。
また、同じくコロナ禍において、ワクチン接種の予約が取りづらい、スマホが使えないといった高齢者を対象としたスマホでのワクチン予約のサポートを、市から委託を受けて実施しました。当然、社協の職員だけでは対応できないため、地域のボランティアや学生、日ごろより付き合いのある支援者などにもお願いしました。特に、社会福祉士など専門職が対応すると、本来はワクチン予約を手伝ってもらうことが目的であるのに、“実は悩みがあって…”と話が広がるなど、普段は地域の居場所や相談窓口に足を運ぶことがない方が、悩みを吐露する場面もありました。これらを振り返ると、まさに重層事業が目指すような「居場所と相談の融合」でした。
https://www.kunitachi-csw.tokyo/








